気になる記事を見かけました。新入社員にアンケートを取ったところ、「年功序列を望む」が「成果主義を望む」を上回ったというのです。
そして過半数を占めるのは今回が初めてということです。
過去35回までは「新入社員は成果主義を望んでいた」ということから見えること。そして今回はなぜ逆転したのか。お伝えしたいと思います。

新入社員へのアンケート結果

さて、話題のアンケートですが、産業能率大学総合研究所が新入社員を対象に実施した調査で、年功序列型の人事制度を望む声が成果主義を上回ったということです。
「年功序列的な人事制度と成果主義的な人事制度のどちらを望むか」という設問に対して、2025年度版の調査で年功序列を望むと回答したのは「年功序列」(14.6%)、「どちらかといえば年功序列」(41.7%)を合わせて56.3%。一方、成果主義を望んだのは「成果主義」(6.5%)、「どちらかといえば成果主義」(37.1%)を合わせて43.6%でした。
「年功序列を望む」が「成果主義を望む」を上回り、過半数を占めるのは36回目となる今回が初めてということです。
「年功序列」を望む新入社員の割合は、22年度の38.9%から徐々に上昇し、24年度に48.5%で過去最高。25年度はさらにこの割合が高まり、記録を更新しました。また、「終身雇用」を望む割合は69.4%、「同じ会社に長く勤めたい」とする回答も51.8%といずれも増加傾向にあるということです。
新入社員としての健全な感覚
アンケートで35年間、新入社員は「成果主義を望む」声が多かったというのは、ある意味、健全だったのではないかと思うのです。
なぜなら、新入社員はまだ若くてこれからの存在です。10年も20年の先のことなんて、遠くの未来で想像もつきません。普通は深く考えたりしないでしょう。
新入社員という立場から見るなら、ただ年齢だけ重ねただけのような上司が自分より多くの給料をもらっていることもまた、理不尽に思えてくるのだと思います。
ですから、新入社員に対して「年功序列を望む」か「成果主義を望むか」という質問に対して、若くても頑張ればたくさん貰える方の「成果主義」を望む声が多いと言うのが、むしろ当たりまえの結果ではないでしょうか。
とするなら、どうして22年頃から年功序列を望む声が大きくなってきたのか、という点について考えてみたいと思います。
ひとつは安定志向から来る「年功序列を望む」という結果
ニュース記事の中にも書かれていましたが、コロナ禍を経て、安心安定を求める新入社員が増えたとあります。それは至極自然なことだと思います。
コロナ禍に限らず、そもそも、会社に勤める第一の理由は、安心して生活を送るためです。
最近の急激な物価高騰も、より安定志向を求める原因のひとつになっているのかも知れません。
成果主義が広がった背景を遡ってみる
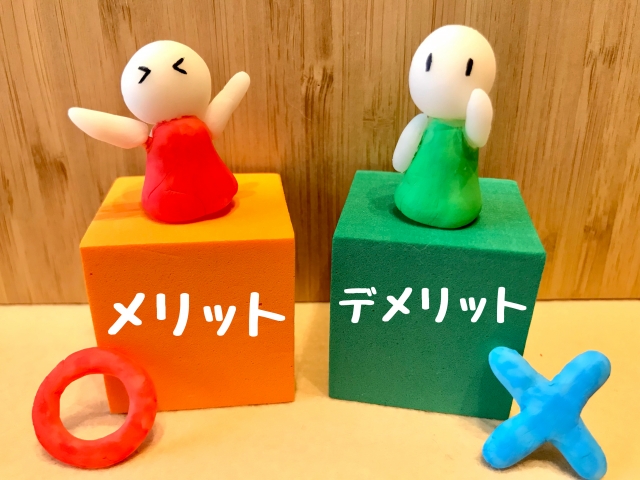
バブル崩壊の1993年頃から、経済誌などで盛んに「成果主義」を取り上げるようになりました。日本経済の低迷から「年功序列・終身雇用では立ち行かない」という考え方が企業側に広がったからです。
しかし、社員の側にはアメリカ的な雇用制度として、カッコ良さや公平性の象徴として「成果主義」が謳われました。
これって、ちょっと納得できないのですが、マイナス要素だけでは、広がらないんですよね。常に喜ばしいような謳い文句がセットなんです。悔しいけれど、政治やマスコミは、人心操作が上手ですよね。
人材派遣が広がったのも、自由な働き方とか、働き方を選択するとか、とにかくカッコ良いイメージが先行したということを聞いています。それを真に受けて会社を辞めて派遣社員になった人から聞きました。これからも、政府や経済界が発信する一見良さそうなものには気を付けていきたいと思います。
実際には成果主義は日本に定着したのか
完全に成果主義に舵をきっている会社は実際には少ないのではないでしょうか?従来の年功序列型に加え、プラスアルファ的なポジションであると思います。また、職種によっても違いますよね。うちの会社でも成果主義は導入していますが、それは完全なる成果主義というより、評価制度を整えて社員から見える化したという感じです。
とは言っても、やはりその評価そのものも、最終的には人間のやることなので、完全に不満が出ないかというと、そうでもないんですよね。「評価」ってとても大切なものなんですけど、またそこばかりに焦点を当てるのも、少し違うかなと思うのです。
実は私、年功序列派なのです。だって、社員の立場からしたら、安心安定した方が嬉しいです。それがいつの間にか、社員の方が「成果主義がいい!」って叫んでるいるのが不思議だったんです。元気いっぱい、やる気いっぱいの新入社員ならまだわかるんですけどね。ドラマやテレビの影響も大きいのかも知れません。
成果主義とキャリアアップと転職、やり過ぎ感たっぷり
ずーっと気になっていたんですが、「社畜になるな」とか「やる気の搾取」とかいった言葉がものすごく流行った時に、影響される人が少なければいいなと思っていました。なぜなら、自分で選んで入った会社なのに、なんだか情けないじゃないですか。せっかく関わるなら、思いっきり愛して、頑張ってみた方が人生楽しいし、幸せだと思うんですよね。その上で、やっぱりこの会社はイヤとか、搾取されている感じがするというのなら、転職を考えればいいのにと。
そして、その「社畜」とセットになって出回っていたのが、「キャリアアップ」と「転職」です。もうそれって何を指すの?システムエンジニアという職種にはある程度通じるかも知れないけれど、私みたいに人事部キャリアってどうなのよ。と、これもまた謎でした。
USJの再建に貢献した森岡毅氏の書いた『苦しかったときの話をしようか──ビジネスマンの父が我が子のために書きためた「働くことの本質」』にも、キャリアの重要性が書かれていたけど、正直言って、そのキャリアを磨けたのも、森岡氏が真摯に仕事に向き合ったからのことだと思うのです。結局、「社畜」にならずに「やる気の搾取」も勘弁してほしくて、「そこそこ」の感じで生きていたら、森岡氏のキャリアは形成されなかったと思うのです。
だから、キャリアアップと転職の前に、そのためには「いまの場所で輝く努力をしないと、何も実らないよ」と、私は声を大にして言いたい!
「成果主義」→「社畜とやる気の搾取」→「キャリアアップと転職」
「成果主義」の延長線上に「社畜とやる気の搾取」があり、そして「キャリアアップと転職」と進んだと思うのです。アメリカ的な個人主義への移行が目的だったのかも知れません。でも結局、この言葉に乗って「転職」をしてしまった人たち、中には成功した人もいると思いますが、そんなに簡単なことじゃないと思います。
実力本位のプロ野球の世界ですら、チームを渡り歩けるのって、ほんの一握りの選手です。プロ野球でのキャリアアップの最終目標は大リーガーですよね。何人いると思いますか?そしてそのプロ野球の構図を一般の企業や社会に合わせてみたら、「キャリアアップと転職」が決して生易しい道ではないことは、誰でもわかると思います。
今回、新入社員が「年功序列を望む」ようになったのは、肌感覚として「キャリアアップと転職」の真の姿が見えてきたのではないか。なんて思うのでした。
日本人は新しいものが大好きなので、一度、流れになると、ズンズン進んでしまいます。あのテレワークもそうでしたよね。テレワークを採用しない会社には未来はない、なんて言う文化人まで現れました。けれど、コロナ禍が過ぎ去って、アメリカの大統領が変わると、また世の中の流れに変化が起きます。
世間の流れに惑わされずに本質を見極める力を養いたいと思うのでした。
